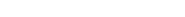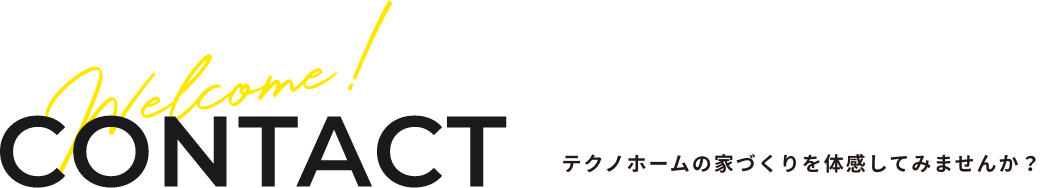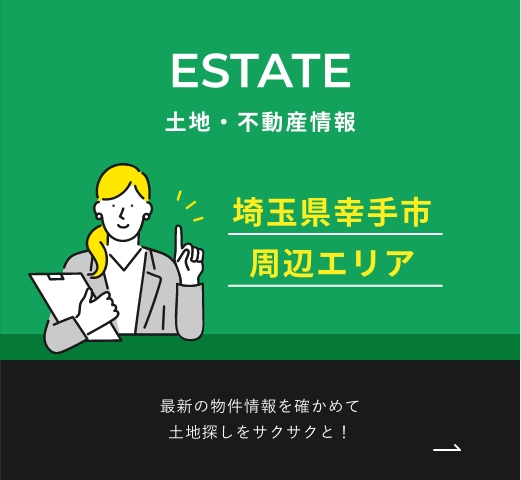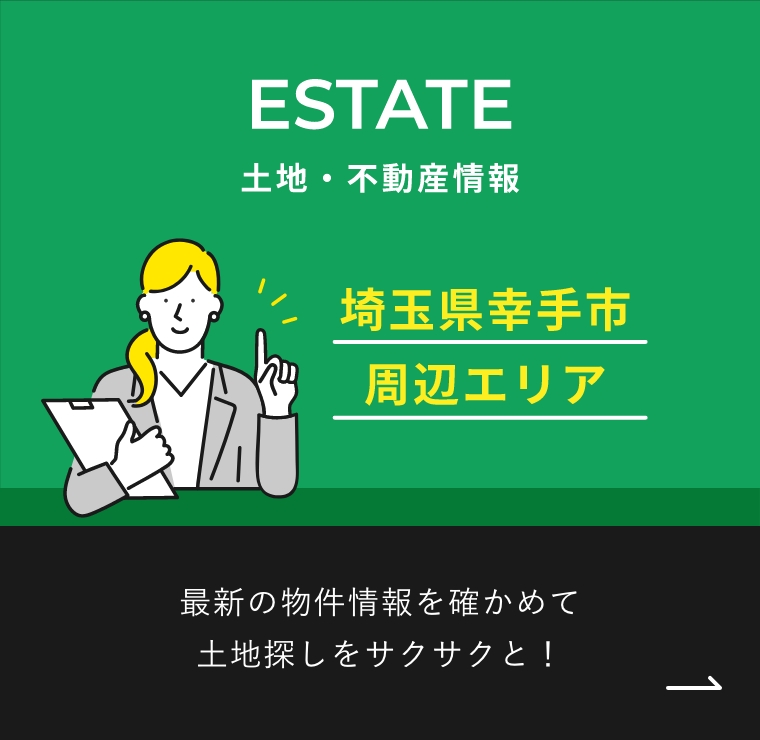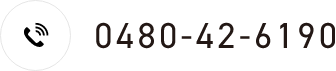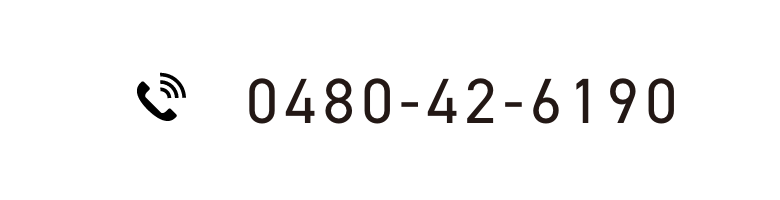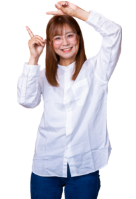家づくり
2025/08/26
家の寿命は平均で何年?材質別寿命の目安と長く住み続けるコツを解説
家の寿命は平均で何年?材質別寿命の目安と長く住み続けるコツを解説
家の寿命は平均約30年とされていますが、実際の耐用年数は材質やメンテナンス次第で大きく変わります。木造・鉄骨・鉄筋コンクリート住宅の寿命の違いと、長く快適に住み続けるコツを詳しく解説します。
こんにちは!埼玉県・加須市、さいたま市、越谷市、幸手市を中心に無垢の暮らしを楽しむBinOの家づくりや、自由設計、新築住宅の販売、リフォーム工事をしている、株式会社テクノホーム/BinOさいたまです!
これから家を建てる方にとって「家は何年くらいもつのか」「どのくらい安心して住めるのか」は重要な懸念点です。とくにマイホームを検討中の方なら、将来のライフプランを立てる上でも家の寿命について正しく理解しておきたいところです。
この記事では、日本の住宅の平均寿命から材質別の目安、家の寿命を延ばして長く快適に住み続けるための方法まで詳しく解説します。家づくりを検討中の方も、すでにマイホームをお持ちの方にも役立つ情報をお届けします。
家の寿命は平均で何年?
国土交通省の「長持ち住宅の手引き」によると、日本の住宅の平均利用期間は約30年です。この数字は取り壊された住宅の平均築後経過年数をもとに算出されています。
ただし、この30年で「家は30年しかもたない」と心配する必要はありません。この統計には、物理的に住めなくなった家だけでなく、ライフスタイルの変化や住み替えなどで取り壊された家も含まれているからです。
法隆寺の木造建築が1300年以上の歴史 を持つように、木造住宅でも非常に長期間の利用ができます。欧米では、アメリカが約67年、イギリスが約81年 と日本より長い傾向にありますが、これは建物の品質ではなく、住宅事情や価値観の違いが影響しています。
出典:「長持ち住宅の手引き」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/tebiki.pdf)
寿命と耐用年数の違い
家の「寿命」と「耐用年数」は異なる概念です。家の寿命は、建物が建築されてから取り壊されるまでの期間を指します。一方、耐用年数は正式には「法定耐用年数」と呼ばれ、減価償却資産が利用に耐える年数です。
耐用年数を超えると、税務上は資産としての評価額がなくなります。つまり、法定耐用年数が過ぎても、その建物に住めなくなるわけではありません。
耐用年数にも種類がある
耐用年数には、法定耐用年数以外にもいくつかの種類があります。
物理的耐用年数
物理的耐用年数は、建物が物理的に使用できる期間です。環境や使用状況により大きく変動するため、一概に年数を定めることは困難ですが、適切なメンテナンスで大幅に延ばすことが可能です。
法定耐用年数
法定耐用年数は、税務上の減価償却費用算出のために定めた年数です。木造住宅22年、軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm以下)19年、軽量鉄骨造(骨格材肉厚3mm以上4mm未満)27年 、鉄筋コンクリート造47年となっています。
経済的残存耐用年数
経済的残存耐用年数は、建物の物理的な面や機能的な面に加えて、市場価値がなくなるまでの年数です。需要と供給のバランスや市場動向により変動します。
出典:「主な減価償却資産の耐用年数表」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
)
【材質別】家の寿命の目安
住宅の寿命は主要構造材によって大きく異なります。適切なメンテナンスを前提とした物理的耐用年数について解説します。
木造住宅
木造住宅の法定耐用年数は22年 ですが、実際の物理的寿命は大きく異なります。国土交通省の資料では期待耐用年数は約65年 とされ、適切なメンテナンスで80年以上、場合によっては100年超 の使用も可能です。
築100年以上の古民家が多数現存し、法隆寺は1300年 以上もその姿を保っています。木造住宅が「寿命30年」 と言われる背景には、税法上の耐用年数やライフスタイル変化による建て替え需要が影響しており、木材の耐久性とは別の要因です。
出典:「指標参考資料1」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/common/001033889.pdf)
鉄骨住宅
鉄骨住宅には軽量鉄骨造と重量鉄骨造があります。軽量鉄骨造の法定耐用年数は19〜27年ですが、実際の寿命は30〜60年 程度です。重量鉄骨造は法定耐用年数34年 に対し、実際は50〜120年 と非常に長期間の使用が可能です。
鉄筋コンクリート住宅
鉄筋コンクリート造住宅の法定耐用年数は47年 ですが、実際の寿命は50〜120年 と長持ちします。高い耐震性、耐火性、耐久性を備え、適切なメンテナンスで100年以上の長期使用も可能です。
【築年数別】家の経年劣化症状は?
家は築年数とともに各箇所で劣化症状が現れます。早期発見と適切な対処で、家の寿命を大幅に延ばすことができます。
築10年
築10年は本格的なメンテナンスが必要になる初期段階です。外壁では塗装の色あせやひび割れが見られます。屋根ではスレート瓦の色あせや塗装剥がれ、金属屋根の部分的サビが発生します。また、水回りでは設備の劣化が現れ始めます。
築10~20年
築10〜20年は、目に外からはわかりにくい部分で劣化が進む時期です。たとえば、給排水管の摩耗や破損による漏水、床下の損傷などが発生しやすくなります。
この頃には、設備の交換や補修など、部分的なリフォームが必要になる場合もあります。また、屋根に関しても葺き替えを検討すべきタイミングに差し掛かります。
築20~30年
築後20〜30年は、以前に行ったメンテナンス箇所が再び劣化してくる時期です。外壁や屋根、給排水設備などに傷みがないか確認しておくことが大切です。
また、この時期は子どもの独立や親の介護など、家族のライフスタイルに変化が生じやすいタイミングでもあります。将来の生活を見据え、バリアフリー化なども含めた大規模なリフォームを検討することもおすすめです。
家の寿命を延ばすコツ
家の寿命を延ばし長期間快適に住み続けるには、日常的なケアから計画的なメンテナンスまでさまざまな対策が重要です。
日々の掃除をしっかりする
日常的な掃除は、家を清潔に保つだけでなく、住宅の寿命を延ばすためにも欠かせない習慣です。
掃除をしながら家の各部位を観察することで、異常を早期に発見できます。たとえば、外壁のひび割れや雨どいの詰まり、床のきしみ、水回りの水漏れなど、小さな変化に気づくことで、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。
定期メンテナンスを実施する
計画的な定期メンテナンスは家の寿命を延ばす最も確実な方法です。
外壁塗装は10〜15年周期 、水栓や配管は5年ごとに点検を実施し、20年を目安に取り換えましょう。小さな劣化や異常を早めに発見することで、安心して長く使用することができます。
長期優良住宅を建てる
新築を検討される方には、長期優良住宅の認定を受けた住まいがおすすめです。劣化対策・耐震性・居住環境など、国が定める9つの基準を満たした住宅は、適切なメンテナンスを行うことで長期間安心して暮らすことができます。
テクノホームでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた「BinO」の規格住宅を通じて、長期優良住宅と同等レベルの高い品質基準をクリアした家づくりを実現しています。
BinOは「住む人の個性を活かしながら、快適で機能的な住空間を実現する」というコンセプトのもと、デザイン性と住宅性能を両立させた規格住宅です。
さらに、厳格な品質管理と充実したアフターサポートにより、多くのお客様から「安心して任せられた」「期待以上の仕上がりだった」と高い評価をいただいています。
住宅診断を検討する
ホームインスペクション(住宅診断)は住宅専門家が建物状態を詳細調査し、不具合や修繕箇所を明らかにするサービスです。将来の大規模修繕リスクを事前把握できる高いコストパフォーマンスがあります。
テクノホームでは、着工からお引渡しまでに第三者機関による10回の厳格な監査を実施しています。この監査は、施工の節目ごとに専門家が品質や施工状況を確認し、必要に応じて是正を行うもので、建物の安全性と耐久性を徹底的に確保することができます。
監査結果は記録として作成され、お施主様に開示・報告いたしますので、住宅の状態を客観的に把握でき、将来的な不具合や修繕リスクの軽減にもつながります。
保険に加入する
自然災害から住宅を守るため適切な保険加入は必要不可欠です。火災保険は火災以外に風災、雪災、水災、盗難もカバーし、地震保険は火災保険とセットで地震、噴火、津波による損害を補償します。
テクノホームのモデルハウスでは、
ちょっと目を引く楽しい家づくりをご体感いただけます。
アイデアの詰まったお家をぜひご覧ください。
家に寿命が来たときの対処法
どれだけ丁寧にメンテナンスを続けていても、家にはいずれ大きな決断を迫られる時期が訪れます。その際に考えられる主な選択肢は次の3つです。
リフォーム・リノベーション
リフォームは、住宅を建てたときに近い状態に戻す修繕のことを指します。一方、リノベーションは、建てたときの状態よりも性能や機能を向上させる改修を行うことを意味します。このような修繕・改修を行うことで、住宅の寿命を大きく延ばすことが可能になります。
大規模な修繕方法として「スケルトンリフォーム」があります。これは構造部分を残し、内装や設備を全面的に刷新する工法で、建て替えに比べて工期が短く、費用を抑えられる場合が多く、仮住まいをせずに済むケースもあります。
ただし、間取り変更の自由度には限界があり、構造補強が必要な場合は追加費用が発生する可能性もあるため、事前の計画と専門家の判断が欠かせません。
建て替え
建て替えは、既存建物を完全に解体し新しい住宅を一から建築する方法です。設計の自由度が非常に高く、現在のライフスタイルに完全に合わせた間取りやデザインが可能で、最新の住宅性能や設備を導入できます。
ただし、工事期間が長く仮住まい費用が必要で、総費用は高額になる傾向があります。
売却して住み替え
現在の住宅を売却し、その資金を新居の購入に充てて住み替えるという方法もあります。売却益を活用することで、立地条件のよい場所やライフスタイルに合った住まいへ移ることが可能です。
住み替えを検討する際は、慎重に計画を立てることが大切です。まず、現在の不動産市場の状況を把握し、売却に最適なタイミングを見極めましょう。新居の購入も同時に進める場合は、資金計画や引越しのスケジュールを事前にしっかり調整することが必要です。
また、売却と購入を同時に行う際には、契約や決済の日程が重ならないよう注意が必要です。さらに、引越し費用や一時的な仮住まいの確保といった予期せぬ出費も想定しておくと安心です。
こちらの記事では、マイホームを購入する際の年収について解説しています。
借入額の目安も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
日本の住宅平均寿命は約30年といわれていますが、これはあくまで統計上の目安にすぎません。実際には、適切なメンテナンスを行えば木造住宅でも80〜100年 以上住み続けることが可能です。
寿命を延ばすためには、日常的な清掃や点検、計画的な定期メンテナンス、そして適切な保険加入が欠かせません。さらに、長期優良住宅のように高い性能基準を満たした住まいを選ぶことで、将来にわたり安心して暮らすことができます。
株式会社テクノホームでは、デザイン性と住宅性能を兼ね備えた「BinO」の規格住宅を通じて、お客様の理想の住まいづくりをサポートしています。高い住宅性能と充実したアフターサポート体制により、長期にわたって安心して快適に暮らせる住宅を提供しています。
これから家づくりを検討される方は、ぜひモデルハウスで実際の住まいを体感してください。お客様一人ひとりの想いに寄り添い、末永く愛されるマイホームの実現をお手伝いいたします。